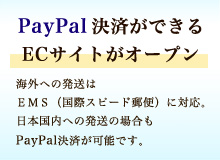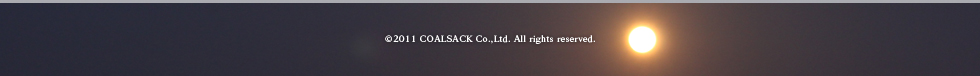鳥巣郁美詩集
『浅春の途』
具象にも象外にもある影と蔭と翳を見据えるとき、そこに力強い生がある。そのことを鳥巣郁美は詩化する。その行先を未見の宙空と位置付ける。おそろしい鋭角の感性に、私は深遠の世界に立たされている。
―山本十四尾(帯文より)
| 栞解説:鈴木比佐雄 |
| A5判/128頁/上製本 |
| 定価:2,160円(税込) |

発売:2010年12月18日
【目次】
Ⅰ
埋まってゆくとき
浅春の途
馬酔木は
カラスと風と
尾根の眼下に
晩夏の風
水引草が
踏 む
柘榴の枝で
山懐が
入り日に
暮 色
微風が
啼く鳥が
打つ雪に
スタイリスト
刻み残して
Ⅱ
歩む者
ひたひたと
誘う道で
足踏む位置から
踏みとった地の上で
壊れる日
生の証
砂の峡で
時のかけらが
過ぎた日は
横 顔
梅雨明けの空
波立つものを
沖深く
エーゲ海
残照の浜
一枚の夜
輝きは
Ⅲ
扉を開けて
部屋隅で
語らいの刻
色濃い影を
川ほとりから
昆陽池
夏過ぎて
花影を踏んで
傾 き
雪渓へ
冬の終り
氷雨の道で
消えた灯は
幼い日 ―離れて暮した息子から―
放つとき ―銃のまわりで―
宿り木の譜
あとがき
略 歴
【詩篇紹介】
「浅春の途」
枯色の野を踏んでいる
来し方の荒涼もまた
寒さを孕んで重なってゆく
名残の冷気の行き戻るその日
裸木はわずかに煙る細枝を持つ
凋落の果てを見透かしてゆく野の
視野の底を熟春が行き交い
是非もない萌色も零れた花々も
紡ぎ誘う果肉の姿も
ずいと続く道程に確かさを弾ませていた
終焉を凝視める如き目前の
途上の陥穽に竦み立つ日
一望の果てに呼び戻してゆくのは
潮騒を呼んだ或る日の堆い海の言伝
虚ろさに挑む分厚い掌
消し色の残欠を煽って
時に耳底に響き残る
夜半にふいと届く梟の声音
共々に見透かす野の終りを不確かに急き蒐めて
更になお立ち戻ってゆく浅春の灯