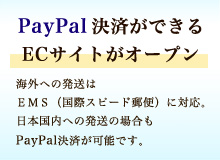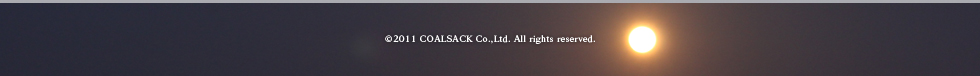生きてきたことと生きていることと 生きていくことを識別しつつも、
内観を常に苦渋に染めながら、石下典子は生と死のあり様を沈思する。
そこから抽象されてくる詩群の美学は
読む人のこころを魅了させずにはおかない。
(帯文:山本十四尾)
| 栞解説文:鈴木比佐雄 |
| A5判/128頁/上製本 |
| 定価:2,160円(税込) |

発売:2008年5月21日
【目次】
第Ⅰ章
神の指紋Ⅰ 10/神の指紋Ⅱ 16/念 20/鷲高隈 24/口中の刃 28/七歳の檸檬 32
線香花火の夜 36/殯 40/墓 地 44/煉り羊羹 48/桜の入水 52/やわらかい女 56
しもつかれ 60/省 く 64/ざわめでくる 68/象の紙 象の風 70/摘 む 74
第Ⅱ章
爪の桜 80/ 水を汲みに 84/素足の女 86/尼 90/得度のピアス 94/涙する文字 98
蘭 鋳 102/覦 み 104/なんどでも莟 106/芹 108/ふたりの女 112/砂 廉 116
潦ひかる 118/ 釘 122
あとがき 126
【詩を紹介】
神の指紋Ⅰ
かたちあるものなら
はじめから
失う覚悟もできる
見えないものはどう守ればよかったのか
こころ死んだ少年の亡霊が
夕飯を食べている
浅く掛けた椅子の猫背に
無言の箸が往復している
平穏を疑わない学校で
おとなが仕掛けていたと誰が思うだろう
未熟なこころをなぶるのはたやすく
ずっと血をにじませていたに違いない
堪えきれず大破するのは必然だった
潜んでいた激昂は一気に噴きあがり
家は淀みに呑みこまれていった
幅広ズボンの裾は黒い尾鰭
爪先で世間に蹴りを入れながら
外股に闊歩しては充たされる一瞬
ひっつめ髪につり上がった目と眉で
寒気を切り裂いて夜通しあてもなく
自転車で漕ぎ回っていた
それでもなお
憤懣の流失は止まず
昂ぶる感情の弧は捩れていく
母を悔悟の総てがしめあげた
荒れ狂う暴風の中で吹き飛ばされぬよう
母ひと文字を杭にして
しかし切なく遣りきれないのは
誰でもない
十五のおまえだった
おまえの母はこの母ひとり
どこまで堕ちてもさらにその下
この手で受けてやる
呪文のように呟けば
うしろ指さされる痛み 謗りの棘なんかどうにでもなる
幼さを隠せないひょろりとした腕の
真ん中の崩れたくぼみ
それは 自らが煙草の火を押し当て
根性焼きと呼ぶ火傷である
生涯の落款 親と子の
だがともかく気が済んだのだ これで
でなければ
自裁の決着をつけていたかもしれぬ
母にはわかる
ひしと腕を握り この世にとどめてくれた
神の指紋