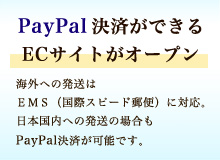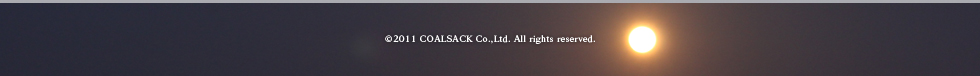<詩作品>
音を聴く皮膚
火傷がなおったばかりの手の甲が
いつの間にか真赤になりけいれんしている
皮膚は覚えていた容赦なく襲った熱を
シタール奏者は激しく弦を爪弾きつづけた
ラビシャンカールの〝夕陽のラーガ〟を
会場はくりかえし打ち寄せる波のターラに熱い海となった
聞き入るわたしは沈む光の飛沫に
全身をぬらし海底に引き込まれてゆく
ラーガとターラのいのちは
新しい皮膚細胞と合体し痛みの振動になった
音がうねる 刺さる
左手で右の腕をかかえこみ蹲っても
肘から肩へ頭へと受け入れた海は鎮まらず
波は強くなるばかり
一瞬自分を失ったとき
波間をよぎる魚の群を見た
それは聖なるガンジス河の水と共に
インド洋の黒潮にのってやって来て
水平線上に沈む陽に染まったターラの魚たち
ふとラーガの海に浸した手の表皮から
時空を越えてすばやくはいりこみ
熱情の尾びれをはねあげ
腹をくねらせて細胞と交合したのだ
魂がふるえ歓喜することが痛みとなる残酷さ
耳をふさぎ音をさえぎっても
皮膚は感応し音を聴いている
耳の不自由な人たちが
大きな風船を両手で抱いて
演奏を聞いているのをみた
掌が音を受けとめ震える
耳というオルガンがなくとも
目で指先で足裏で音を感じている
今わたしの手の甲も
*1 ラーガ=インド音楽の旋律
*2 ターラ=インド音楽のリズム
静かな夕べ
玄関をあけると
隣家の坊やが立っていた
ティッシュに包んだ小鳥の卵を
私の前に差し出して
「巣から落ちてたの どうしたらいい?」
と訊く
ムク鳥が小枝を咥えてきて
家の脇の花水木にせっせと巣をつくっていた
オスとメスが忙しく電線の上ですれちがう
鳴声を交わしながら営みをつづけ
葉を繁らせた枝に
わずかな春風にも落ちそうな
つつましい巣をつくった
卵を抱く母鳥
その姿を見た者は
挨拶がわりに人に教える
「あたためているよ」
枝の下でいつもどおり繰り返される
気を遣わない視線とおしゃべりの散歩
登校下校の小学生達も指を差す
「尾がみえる いる いるよ!」
そのたびに鳥は飛び立ち
電線に止って甲高く鳴いた
ある日卵は地面に落ちた
母鳥が巣からけ落したのか
そのまま飛び去り帰ることはなかった
巣の下の草むらで卵をひろったキミは
ふた晩箱に入れ抱いて寝たと言う
付き添う若い母親の困惑顔と共に
卵は私に渡されようとしている
「私は母鳥にはなれない
その卵はキミの家の庭に埋めましょう」
それから私は何も言わないで土を掘り
キミは掌の中ににぎりしめていたものを
ポトッと穴に入れ
小さな手を合わせた
このできごとが心に残っているあいだは
キミの耳に巣の中のみえない雛の声が聞こえているだろう
夕暮れが花水木の影を消しはじめると
沈黙の月が満ちた