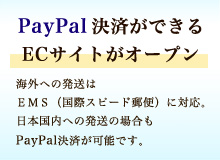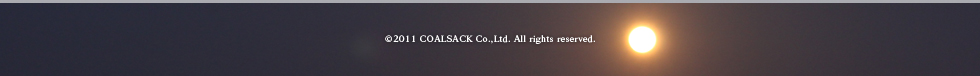秋山 泰則 (あきやま やすのり)
経歴
昭和十三年 九月、東京都浅草に生まれる。
昭和二十年 四月、長野県松本市近郊に疎開。以後、現在まで松本市に在住。
昭和三十二年 長野県立松本深志高校を中退。詩誌「WILL」発刊。
昭和三十四年 自営業を開始、現在に至る。
昭和四十年 長野県詩人協会新人賞受賞。詩集『流砂』刊行。詩展開催等現在まで活動を続ける。
昭和四十二年 長野県詩人協会幹事長。
昭和四十五年 長野県鮨商組合理事・監査役。
昭和四十八年 市民タイムス文芸欄「詩」の選者となる。
昭和六十年 鎌田小学校PTA会長。
昭和六十一年 松本市立信明中学校校歌を作詞。
昭和六十二年 鎌田中学校PTA会長、松本市PTA連合会会長。
松本市議会議員に初当選。同市監査委員、議会運営委・教育民生委・経済環境委・決算特別委 各委員長他を歴任する。
昭和六十三年 高山植物等保護指導員に就任する。文芸講座(自分史)を開講。
ぼんぼん青山様伝承保存会設立に参加。運動が実り「松本市」「長野県」の無形民俗文化財に指定される。同伝承保存会実行委員長。
平成三年 松本市公設地方卸売市場買出人組合組合長に就任。
平成十三年 文芸講座(現代詩)を開講。松本詩人会設立。詩誌『松本詩集』を刊行。
第一回美ヶ原高原詩人祭を企画・開催(毎年開催)。
平成十五年 松本市議選・五期目に落選。
平成十六年 松本市文化芸術振興審議会会長に就任。
平成十七年 長野県自然観察インストラクターとなる。松本市子供を守る会を設立。
平成十八年 地球温暖化防止推進委員となる。
平成十九年 詩集『民衆の記憶』発刊。
平成二十二年 詩集『泣き坂』発刊。
昭和十三年 九月、東京都浅草に生まれる。
昭和二十年 四月、長野県松本市近郊に疎開。以後、現在まで松本市に在住。
昭和三十二年 長野県立松本深志高校を中退。詩誌「WILL」発刊。
昭和三十四年 自営業を開始、現在に至る。
昭和四十年 長野県詩人協会新人賞受賞。詩集『流砂』刊行。詩展開催等現在まで活動を続ける。
昭和四十二年 長野県詩人協会幹事長。
昭和四十五年 長野県鮨商組合理事・監査役。
昭和四十八年 市民タイムス文芸欄「詩」の選者となる。
昭和六十年 鎌田小学校PTA会長。
昭和六十一年 松本市立信明中学校校歌を作詞。
昭和六十二年 鎌田中学校PTA会長、松本市PTA連合会会長。
松本市議会議員に初当選。同市監査委員、議会運営委・教育民生委・経済環境委・決算特別委 各委員長他を歴任する。
昭和六十三年 高山植物等保護指導員に就任する。文芸講座(自分史)を開講。
ぼんぼん青山様伝承保存会設立に参加。運動が実り「松本市」「長野県」の無形民俗文化財に指定される。同伝承保存会実行委員長。
平成三年 松本市公設地方卸売市場買出人組合組合長に就任。
平成十三年 文芸講座(現代詩)を開講。松本詩人会設立。詩誌『松本詩集』を刊行。
第一回美ヶ原高原詩人祭を企画・開催(毎年開催)。
平成十五年 松本市議選・五期目に落選。
平成十六年 松本市文化芸術振興審議会会長に就任。
平成十七年 長野県自然観察インストラクターとなる。松本市子供を守る会を設立。
平成十八年 地球温暖化防止推進委員となる。
平成十九年 詩集『民衆の記憶』発刊。
平成二十二年 詩集『泣き坂』発刊。
【詩の紹介】
母がうたう歌
若い頃の母が口ずさんでいた流行歌が
前触れも無く口を衝いて出ることがある
女であるがゆえの理不尽な仕打ちを
黙って耐えていた後に
放心したような姿で ふっとうたう
私は母の何もかもが好きであったが
とりわけ
女の悔しさをあらわす仕種は美しいと思った
その心情もさることながら
闘って敗れた姿には
宝石をばら撒いたような華やかさと
誰も近付くことのできない厳しさがあった
母がうたった歌をうたってみると
私の何処かで小さな光りが
群がって湧き出ようとしているのを感じる
その歌に見出した母の思いが伝わって来る
故郷を失った人間の哀しさと 流離うことの虚しさを
闘いながら教えてたのかもしれない
どんなに言い繕っても戦争が正しいわけは無いと
昼の星
日の丸一本振られるでなく
見送る人もいない出立が
俘囚の生活の始まりであった
武器を持たない兵士の闘いは
身を守るためにひたすら 逃げ回ることであった
前線の兵士は戦うべき敵をもっていたが
銃後の兵士は敵でないものと戦わなければならなかった
深い穴の底から空を見ると
昼でも星が見えるという
母はきっと沢山の星を見たことだろう
光を持たない黒い星と
深い穴の底でしか見る事ができないと言われる
真っ黒な太陽も見ただろう
命が惜しかったから逃げた
死にたく無いから故郷を出た
その引き換えに与えられたもの
これはいったい何なのだろう
燃えて死んでも東京に居ればよかった
山あいに大きくうねりながら消えていく
汽車の煙りを見ながら誓った事は
あの先へ どうしても帰らなければならないと言う
たった一つの事であった