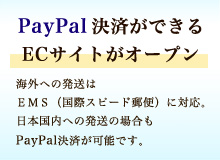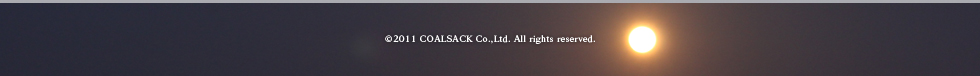<詩作品>
一遇
―百武すい星に寄せて―
二万年前、
そのまた二万年前にも、
やはりだれかがあの星を見ていたのだろうか。
あるいは鳥や獣や森の木々、
(すべての生き物の祖先たちが……)
気の遠くなるような はるかな時間と空間を駆けて、
彼はぼくらの世界にやって来たのだ。
(ああ、ぼくらもみな本当は、
万に一つも出会いがたい
はるかな存在だったのではないか。
なのにこうして、
愛し合ったり、悲しみを分かち合ったりする。)
あの尾はじつは尾ではなく、
太陽風に吹かれて噴き出す光の帯だという。
そしてぼくらの中にも、
ああした燃えながら閃光する
何かがないか、
すべての出会い、別れるものに優しく
たむける愛のような。
二 人
それは小さなヨーロッパの田舎風といった感じのレストランで
そこを通るたびにいつも思い出す
ちょうど小学生になったばかりの娘と二人で
ここでランチを食べたことがあった
たしか開店してまもない頃のことで
ここでどうしても食べてみたいと娘が言い出して
じゃ、パパと二人きりでもいいかと聞くと
だいじょうぶ、一人でも食べられるからと
そこで二人で初めて二人きりのランチを食べた
その日、
春のやさしい雨がふっていた
まるで雨までがヨーロッパの田舎風だった
二人、テーブルに向き合って座り
ランチを注文し
何も言うことなく ただ二人
心待ちに 楽しみに 美味しい料理が出てくるのを
じっと待った
やがて
ほかほかのオムレツと大きな丸いパンが運ばれて
甘いバターの香りを嗅ぎながら
しんに楽しい食事をした
たどたどと食べては休み 休んでは食べている
おまえを見るともなく 見ながら
ゆっくりとゆっくりと、私は食べた
今でも
そこだけ見えない光が当たっていたような気がする
たとえ異国の
知らない言葉を話される神様であっても
そのときは そのときだけは 私たち二人をやさしく
そっと見守っていてくれた気がする。
いたたまれない日
一人うらぶれて心暗くくもる日
ふる雨を見るともなく見ながら あの日のことを思い
そっと心をなぐさめる。