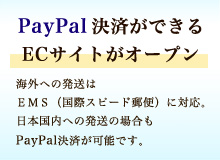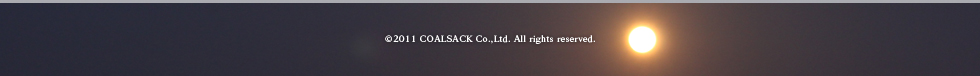『人新世(ひとしんせい)の生活世界詩歌集 ――気候変動・戦災・核災をもたらす科学技術偏重から始原の存在へ』公募趣意書
◆発 行 日=日本語版2025年8月
◆編 者=鈴木比佐雄、座馬寛彦、鈴木光影、羽島貝
◆発 行 所=株式会社コールサック社
◆データ原稿の方=〈m.suzuki@coal-sack.com〉(鈴木光影)まで
【よびかけ文】
宮沢賢治『春と修羅』は、全七〇篇と補遺九篇の計七九篇が収録され一九二四年四月二〇日に刊行された。中心的なテーマは妹トシを悼む詩「永訣の朝」などの鎮魂だ。詩「火薬と紙幣」は最後のパート八の「風景とオルゴール」の中に収録され、二連目に「森はどれも群青に泣いてゐるし/松林なら地被もところどころ剝げて/酸性土壌ももう十月になつたのだ」と記している。賢治が後に岩手の酸性土壌を改良するために肥料設計などを実践していくことの原点がこの詩行から読み取れる。私が最も感銘を受けるのが最後の五行だ。岩手の天空と野原を瞬間にその風景と賢治の内面が一体化されているからだ。そして本当に価値のあるものとは何か、また「ほんとうの幸福」とは何かを問い掛けてくる。賢治なりの答えは「野原をおほびらにあるけたら/おれはそのほかにもうなんにもいらない/火薬も燐も大きな紙幣もほしくない」だったのだ。「火薬」とは「兵器」、「燐」は「鬼火」、「紙幣」は「富」などを比喩として表したのだろう。賢治は詩人・童話作家であり、現代から見ると地球環境を考えて実践するエコロジストの先駆者であった。賢治は『春と修羅』の序で、地質学の「新生代沖積世」の中での生き物たちは(あるいは修羅の十億年)とも示唆している。「新生代沖積世」は現代の地質学では「完新世」と呼ばれている。
「人新世」(Anthropocene)とは、ノーベル化学賞受賞者のパウル・クルッツェンが提唱した考えで、氷期が終わる一万一七〇〇年から現在まで続いてきた「完新世」の後に、「人間たちの活動の痕跡が、地球の表面を覆いつくした年代という意味」で名付けられた。賢治が亡くなった一九三三年から数年たった一九三六年頃に、ナチスに追われたユダヤ人で「現象学」を提唱したドイツの哲学者フッサールが『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』を執筆した。その中で「客観的科学」の「論理学」は「仮象」でありながらも絶対的なものとして我々に迫ってくる。実はそれを生みだした背景には「生活世界」があると言い、「生活世界」の「主観的―相対的な真理の領域」が源泉であることを「生活世界」の「論理学」として記した。
「生活世界」(Lebenswelt)はフッサールの用語であり「あらゆる科学的探究に先立って、われわれの生活が営まれている、現実として直接的に経験されている、日常的世界のこと」と語っている。
その試みはまたハイデガーが古代ギリシャ哲学から存在が「本質存在」と「事実存在」に分離し「本質存在」を優先させてきた存在忘却の歴史に対して、その二つの存在の原点である本来的な「始原の存在」(ピュシス)へと立ち還らせ、私たちに将来の「始原の存在」を創造的に問い掛けてくる。そのような観点から二〇二五年の詩歌集タイトルを『人新世の生活世界詩歌集――気候変動・戦災・核災をもたらす科学技術偏重から始原の存在へ』とした。
賢治の詩以外の作品例として、俳句では永瀬十悟氏の〈鴨引くや十万年は三日月湖〉では、鴨が北方に渡っていく様を見て、十万年後には、放射性物質が半減し、今も存在する帰還困難地域で取り残された三日月湖のような原発の周辺が動植物の楽園になっていて欲しいと語っている。
短歌では本田一弘氏の〈福島の土うたふべし生きてわれは死んでもわれは土をとぶらふ〉では、たとえ放射性物質で産土が汚染されようとも、われは詠い、死んでも産土を案じて訪ねてくると語り、故郷の産土が汚染された言い知れぬ悲しみを伝えている。このような地域に根ざした発想で、「人新世」の特徴である、
①地球温暖化などの気候変動、
②森林地帯を開発し生態系を破壊する生物多様性の喪失、
③プラスチック等の人口物質の増大、
④化石燃料の燃焼による二酸化炭素の増大、
⑤核実験・核兵器による放射性物質の残存など、
人類の科学技術偏重の活動が地球に破滅的な影響を与える事実を踏まえ、身近な地域環境の変容の発見を伝え、本来的で創造的な「始原の存在」に問い掛ける詩歌を寄稿して頂きたい。
(鈴木比佐雄 記)