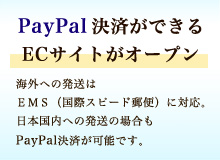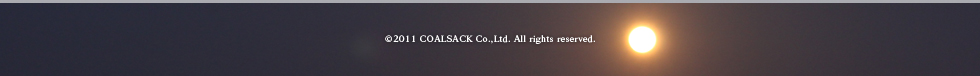石炭袋新書評論集
象徴としての〈港〉。それは、こころのあり方の選択である。交信が生む宇宙論的な人のつながり。文字の連なりが伝える世界とこころの深部。そこに詩文学の素晴らしさがある。新世紀の荒波に、原初からの時空を遍在する詩精神の灯台は何を照らし、汽笛はどのように鳴るだろう。(第三章「港の詩想」より)
| A5判/392頁/ソフトカバー |
| 定価:2,160円(税込) |

発売:2011年11月24日
【目次】
第一章 海、港、詩
海、港、詩
第二章 人生は詩かもしれない
人生は詩かもしれない ① 横浜
人生は詩かもしれない ② 横浜
人生は詩かもしれない ③ フィンランド
人生は詩かもしれない ④ フランス
人生は詩かもしれない ⑤ 大阪
人生は詩かもしれない ⑥ 東京
第三章 詩想の港
詩の広い場所へ ~夏の詩の学校講義メモ~
現代詩の新たな可能性を求めて
詩の力
コスモポリタンの詩学
現代芸術の多様な形態へ
いまなぜ詩なのか ~福井「水脈」二十周年のつどい記念講演~
港の詩想
第四章 二十一世紀に生きる古典の魅力
二十一世紀に生きる今野大力 今野大力没後七十五周年のつどい記念講演(旭川)
今野大力への手紙 ~「今野大力没後七十五周年のつどい」を前に~
二十一世紀に生きる小熊秀雄
小熊秀雄への手紙
河邨文一郎詩集『物質の真昼』を読む 大阪・詩の講座
二十一世紀と濱口國雄の詩
戦後の名詩・木島 始「日本共和国初代大統領への手紙」
戦後の名詩・黒田三郎詩集『小さなユリと』
戦後の名詩・関根 弘「革命」 アヴァンギャルドな下町ダンディ
二十一世紀に生きる古典の魅力 ① まずは笑いましょう
~ダンテ、ラブレー、アポリネール、ボリス・ヴィアン~
二十一世紀に生きる古典の魅力 ② 視点はお隣りの小さないのちに ~ブレヒト~
二十一世紀に生きる古典の魅力 ③ 夢の炎はひっくり返っても燃えている ~アポリネール~
第五章 現代詩時評
現代詩時評 八月、長崎にて
現代詩時評 詩学的進化論の大空で
現代詩時評 同窓会よりも共感を覚えるもの
現代詩時評・展望 地球は回り、社会は動き、詩は降り注ぐ
現代詩時評・展望 詩人の言動 ~時代の闇と、詩の光~
現代詩時評・展望 アンソロジーから見えるもの ~個であると同時に人類である~
第六章 夕焼けランデブー
夕焼けランデブー ① 地球という詩
夕焼けランデブー ② いてまえ打線の夜
夕焼けランデブー ③ 心の密度
夕焼けランデブー ④ 秋、なんばの雑踏にて
私の原点
第七章 現代の生きた詩書
『命が危ない 311人詩集―いま共にふみだすために―』 命の声の詩集です
『鎮魂詩四〇四人集』 引き継いでいくもの ~あじさい花の季節に~
亜久津歩詩集『いのちづな』 リアルタイムのこころの闇と光
おぎぜんた詩集『アフリカの日本難民』 現実と存在の凝視
大森ちさと詩集『つながる』 殺伐とした現代にしみこむこころの言葉
平井達也詩集『東京暮らし』 現代社会の苦味とリアルな生活実感
尾内達也詩集『耳の眠り』 世界の深淵を聴きとる詩精神
中林経城詩集『鉱脈の所在』 現代世界にひろがるみずみずしい新古典詩精神
井上優詩集『厚い手のひら』 かなしみを手のひらの体温で包む光の詩集
谷崎眞澄詩選集一五〇篇 現代社会のただなかに降る雪の詩精神
山岡和範詩選集一四〇篇 にんげんをかえす、けやきの詩人
くにさだきみ詩論集『しなやかな抵抗の詩想』 詩を通じて時代と生き方を見つめる目
くにさだきみ詩選集一三〇篇 ほとばしる批判精神とたくましい生命力
斎藤彰吾詩論集 『真なるバルバロイの詩想――北上からの文化的証言(1953―2010)』現代詩のアテルイが放つ北上の詩想
鈴木比佐雄詩論集『詩人の深層探求 ―詩的反復力Ⅳ(2006―2011)』 刊行に寄せて
大井康暢全詩集 戦後詩・現代詩の大切な達成
石村柳三詩集『合掌』 あるがままの命の合掌
『相馬大詩集』(新・日本現代詩文庫⑪) 詩集『西陣』を中心に
下村和子詩集『弱さという特性』 ―現代世界に切実な命の逆説、個の詩想
吉川伸幸詩集『今届いた風は』 本当の強さは優しさから生まれる
伊藤眞司詩集『ボルト』 草の根からの戦後詩本流
小泉克弥詩集『無理を承知の水の星』 無理を承知のロマン
葵生川玲詩論集 『詩とインターネット ―戦後からのまなざし―』 時代社会と向き合う詩精神展開
久保田穣詩論集 『栗生楽泉園の詩人たち』
柴田三吉詩集『非、あるいは』 痛みを引き受ける深み
中正敏詩集『いのちの籠・2』 詩的内省の批評眼
北畑光男詩集『死はふりつもるか』
新井豊吉詩集『横丁のマリア』
なたとしこ詩集『地図帳のない時間へ』
中村花木詩集『ぶらんこ』
只松千恵子詩集『赤い紐でしばられ』
下前幸一詩集『ダンボールの空に』
詩誌評 ① もう一度 夢をみる
詩誌評 ② 届けたい想いを持つ人
詩誌評 ③ 約束
詩誌評 ④ 対岸にいて気づく
詩誌評 ⑤ 佇んでいると
詩誌評 ⑥ いい音がする
詩誌評 ⑦ 生きている詩
詩誌評 ⑧ 思いがけなく
詩誌評 ⑨ ここもその場所
詩誌評 ⑩ そっとエールを
詩誌評 ⑪ 耳の奥の方から
詩誌評 ⑫ いつもおうえん
第八章 ひと、文化、文学
静御前のうたが聴こえてくるまで ~現代社会と現代詩のもうひとつの視点~
車社会の廃絶
ただ散歩するだけの大切さ
旅ごころは平和の詩ごころ
ロック批評と学生時代の記憶
旭川文学資料館を訪れて
追悼 福中都生子さん
詩人・増岡敏和さんへの私の感謝
夏、亡き人々を思う
ハマのセミ、いとかなし
初出一覧
あとがき
略 歴
海、港、詩
海と陸とヒト
水が山や森や平野を通り、陸地の尽きたところに出ると、そこから先は海と呼ばれる。現在は土の表面になっているところも大昔は大洋の底だったりするし、いまは海底のところがかつては陸地だったりするから、海に関する場所はこの星の大部分と言っていいだろう。
私たちヒトは酸素がないと生きていかれない。もっぱら陸地に暮らしていて、水上暮らしの部族にしても、川や海の水中ではなく、小屋や船などを工夫して空中に住んでいる。大津波や大洪水が暮らしを破壊する危険の中で。
私たちはたびたび海を見つめる。
すべてがそこから鼓動を始めた場所として。
遠い祖先は何のために魚類をやめたのだろうか。そして、何のために両生類からもはみ出して、爬虫類でさえ満足できずに、夜行性小動物の苦労までしてやがて哺乳類へと転身していったのだろうか。
確かなことは、いずれの時代も、変化していく地球環境のもとで、必死に生き延びてきたということだ。
私たちが直立二足歩行を定着させて、かなりの時間が経過した。
アフリカから地球の表面いっぱいにひろがっていった移住者たちは独自の文化をつくり、それぞれの環境の特徴や個性を遺伝子に付け加えていったが、その違いの大きさに負けないくらいの大きな共通性ももっていた。
暮らし方も地域感情も民族も文化も違うのに、海の向こうとこちらで手紙も電報もラジオもテレビも衛星通信もインターネットもなかった時代からの長い長い時間に、ヒトすなわちホモ・サピエンスは地球という柵のない動物園の一つの種として、いつしか人類を形成していった。
人類であると同時に、個人である。現代のヒトはその複雑な関係の中に生きている。
人類史
人類は喧嘩が絶えない種としてやっかいだった。
恐竜支配の時代とヒト支配の時代、相対的にどちらがましか、判断する客観的第三者はいない。なぜなら、そのスケールの脳髄をもつにいたったのはヒトだけだから。
人類の規模をもつにいたったヒトすなわちホモ・サピエンスは、その内部が細かい差異をもつ集団に分かれていて、さらには個人という強い差異をかかえている。
身体における差異と同じくらいに複雑なのは、心の差異であろう。彼らそれぞれが話したり書いたりする言葉というものや、それを通じて判明する脳の発信や内面すなわち心を見るならば、七十億通りくらいの枝分かれが確認できる。
よくもこんなに多様なヒトが共存してきたものだ。
実際、その困難は無数の残虐な戦争や、彼らが各地でつくっていった社会システムにおける衝突・争い・支配となって表面化した。
生き延びるための食物の奪い合いから始まって、土地の奪い合い、異性の奪い合い、などがあり、現在では、彼らヒトがつくり出して長く威力を発揮している金銭というものをめぐる生活格差、彼らがつくり出した宗教や思想というものの対立、あるいは長い歴史をさかのぼるように原初をむしかえす民族や出自などの対立、なども深刻である。ゲンシリョクというもののとりかえしのつかない開発による人間破壊もある。
エネルギーが大事だと言って、浴びたらヒトが死ぬものを推進している。
武器が発達しすぎて、とうてい使う予定のない武器までつくらないと企業がうるさいしくみになった。
世界の貧しいヒトたちに援助をと言って、足もとの貧しいヒトたちは放っておく。
愚かだと思うだろう。しかし、その愚かなところからいまだに抜け切れないのが、ヒトなのである。同時に、これではダメだと気づいて、新しい共存へ、脳髄思考と文明方向の新しい進化をとげようという向きを内部に増やしつつあるのも、ヒトである。
ヒトと詩、詩と文学
そんな人類は、詩というものを発生させ、長い間、愛好してきた。不思議なことに、地球いっぱいにひろがったいずれの地域にも、詩があった。
やがて互いの言語を理解しあって翻訳という技術によってそれぞれの詩を伝えると、これまた驚くことに、共感というものが成立して、豊かな個性を通じた類の内面的共通性が明らかになったのである。
詩はどこから生まれたのだろう。
狩猟採集や牧畜、農耕の作業のかけ声やうたなど労働の現場からだと言うヒトもいるし、呪術的なまじないやお祭りの声からだというヒトもいる。原初的な言葉の伝達そのものから生まれたかもしれないし、ひょっとして愛の告白からかもしれない。
私はそのいずれも当たっていると考える。これらの生き生きとした人間の発声が歴史的にいろいろまじりあって、詩の豊かさを形成していったのではないだろうか。
その想像は楽しい。
脈々と続き、さまざまに変化して、類の伝統と個の革新、地球中でヒトが残してきた詩という不思議なもの。
詩は小説よりも古くからあり、言葉を使った芸術ではおそらく最古のものと言えよう。言い方を変えれば、小説も戯曲も随筆も論説文も、すべては詩から始まったということだろう。
すべての文学の母、その詩には、当然、短歌・俳句・川柳や歌詞も含まれるし、中国の漢詩も西洋の伝統詩も中東の古典詩もすべて含まれる。
詩文学による心の人類的なつながり。
それは、人類の惨たらしい側面とは対照的な、ヒトに生まれた真の生き甲斐、真の感動ではないだろうか。
詩の港
詩が文学の母ならば、その詩をつくり出したヒトの生命の始まりは海である。
海にヒトが関わる場所が港ならば、詩はヒトの心の文学的な港である。
港にさまざまなヒトや文化が入ってきて、港からさまざまなヒトや文化が出ていくように、詩にはさまざまな心が入ってきて、詩からはさまざまな心が旅立っていく。
酸素と太陽を欲して私たちは陸に立っている。
多忙で複雑な現代社会。
その中でふと、忘れがたいふるさととして、海に帰りたくなる。
それは、漁業や商売や貿易や運輸をなりわいとして海男・海女を生きている人々だけではない。
多くの人々が海に出かけて、泳いだり、もぐったり、釣りをしたり、舟を出したり、波打ち際ではしゃいだり、じっと見つめて佇んだりするのだ。陸上に暮らしながら、いつも気になっている海の存在。
鳥の真似をして空を飛ぶことが遠い種へのあこがれの実現ならば、魚の真似をして海を行くことは遠い体の記憶の再現なのかもしれない。
そして、ヒトは港に集う。
ひろがる世界に向かって、人生の何かに向かって。
海の港にも、空の港にも、心の港にも。
心の港、それが詩だ。
原点
犯行現場に戻る犯人の心理に似て、私は詩的原点の港に帰る。
海にとりつかれてしまったのは、こどもの頃から横浜の港や湘南の砂浜で遠くを見つめていたからかもしれない。
海からは何が見えるだろう。
連綿と打ち寄せる多言語の合唱は水のダンス。
その形はさまざまで、好き勝手に踊るそれぞれが、どこか大きいところで有機的につながっている。
波音を聴きながら、地球のふところへ精神が解放される。
海は、少なくとも自分がこの星の子であることを教えてくれる。
人生の不安も、世界の激動も、海に来るとすべてがつながり、ちっぽけだと感じられていた存在が、重く受けとめられる。
かなしみは社会生活においては抑圧されることが多い。デジタルなハイペースの現代は、システムの日々更新をモットーとしているから、個人の非生産的な立ち止まりは歓迎されないばかりか、許されないことさえある。
最先端のホモ・サピエンスが、内面精神もコンピュータや自動車並みに操作しようとしても、ひとりひとりの人間は、動物であり、哺乳類であり、DNAに深く刻まれた海からの地球の生きものである。
進化をとげたとするならば、そのような血の通った生きものである自分を客観的に発見できる点にあるだろう。
キリンもゴリラも、愛したり、可愛がったり、悼んだりする温かい血をもっている。
そこから外れていくことが進化だと勘違いした人類が、キリンやゴリラの愛をさらに深めていくことこそが進化であると方向転換できるかどうか。
ホモ・サピエンスにだけ与えられた高い知能は、何のためにあるのか、その真価が問われる。
心。
内面の広大な宇宙。
そこに
ぽっ、と
かなしみ。
癒やし。
励まし。
希望。
怒り。
喜び。
勇気。
夢。
手渡されるものが、胸に灯る。
発せられたものが、波をうつ。
凍っていたものが、流れ出す。
立ちすくむものが、歩き出す。
受けとめられたものが、投げ返される。
孤立していたものが、手をつなぐ。
そっと、ひとりのヒトが、感じ入る。
それを、詩と呼びたい。
生きていることの大切さ、
そう言ってもいいかもしれない。
そして時代の汽笛が鳴って
詩の港から、人間が出航する。
詩の港へ、人間が帰港する。