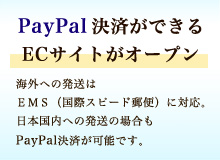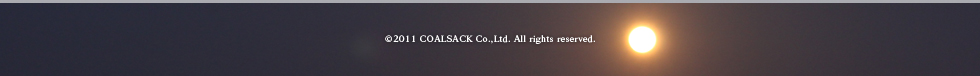安永圭子詩集
『音を聴く皮膚』
哀の背は愛、愛のとなりは哀。それは生きているものすべての透視図。
的確、端正な場景表現。多様な心層の見事な織模様の詩群。
それらと円居して安らかな心になるのは私だけではない。
―詩人・山本十四尾(帯文より)
| 栞解説:鈴木比佐雄 |
| A5判/136頁/上製本 |
| 定価:2,160円(税込) |

発売:2010年10月18日
【目次】
Ⅰ章 音を聴く皮膚
音を聴く皮膚 10
初夏の蛇 14
木精 16
さびしい庭 20
静かな夕べ 24
壜の中 28
扉の中のグラス 32
老女の日日 36
月 齢 40
木 霊 44
Ⅱ章 海辺の情景
しだれ桜の景 50
琵琶湖の十一面観音 54
海辺の情景 58
夏の終り 62
おちた蝶 66
高野山奥の院 72
深大寺十三夜祭 76
晩秋の沼 80
旅 84
桑の木 86
Ⅲ章 彼岸花
彼岸花 92
母の背中 96
白綸子の小袖? 100
白綸子の小袖? 102
野馬が駈ける 104
ふる敷 108
ヒュルヒュルと咽を通る 112
飛べ飛べ自転車 116
居場所 120
彼方の青 124
冥界からきた蛙 128
あとがき 132
略 歴 134
【詩篇紹介】
音を聴く皮膚
火傷がなおったばかりの手の甲が
いつの間にか真赤になりけいれんしている
皮膚は覚えていた容赦なく襲った熱を
シタール奏者は激しく弦を爪弾きつづけた
ラビシャンカールの〝夕陽のラーガ(*1)〟を
会場はくりかえし打ち寄せる波のターラ(*2)に熱い海となった
聞き入るわたしは沈む光の飛沫に
全身をぬらし海底に引き込まれてゆく
ラーガとターラのいのちは
新しい皮膚細胞と合体し痛みの振動になった
音がうねる 刺さる
左手で右の腕をかかえこみ蹲っても
肘から肩へ頭へと受け入れた海は鎮まらず
波は強くなるばかり
一瞬自分を失ったとき
波間をよぎる魚の群を見た
それは聖なるガンジス河の水と共に
インド洋の黒潮にのってやって来て
水平線上に沈む陽に染まったターラの魚たち
ふとラーガの海に浸した手の表皮から
時空を越えてすばやくはいりこみ
熱情の尾びれをはねあげ
腹をくねらせて細胞と交合したのだ
魂がふるえ歓喜することが痛みとなる残酷さ
耳をふさぎ音をさえぎっても
皮膚は感応し音を聴いている
耳の不自由な人たちが
大きな風船を両手で抱いて
演奏を聞いているのをみた
掌が音を受けとめ震える
耳というオルガンがなくとも
目で指先で足裏で音を感じている
今わたしの手の甲も
*1 ラーガ=インド音楽の旋律
*2 ターラ=インド音楽のリズム