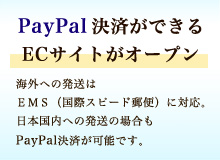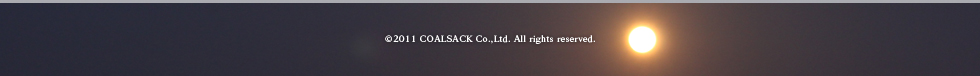秋山泰則詩集
『民衆の記憶』
従兄の肺病は 軍隊で無理をしたせいだといった/私が近付くと 近付いた分だけ離れた/母が近付いても やはり離れた/離れた分が従兄の愛で 離れた分の寂しさをこらえた事が/私達の愛であった
(「戦死」より)
| 栞解説文:鈴木比佐雄 |
| A5判/104頁/ソフトカバー |
| 定価:2,100円(税込) |

発売:2007年4月3日
【目次】
1章 ぼくは兎になりたかった
ぼくは兎になりたかった 10/母という字 12/母がうたう歌 14/初冬の川原にて 16
流れと群れ 18/赤い舌 20/母の背中 22/戦死 24/生きる形 26/声 28
沢蟹 30/父の日 32/虫捕り 34/幸福 36/遠足 38/あした天気に…… 40
望郷 42
2章 火が燃えている
火が燃えている 48/立ち話 50/美しいとき 52/母の声 54/オラショ 56
二十一番目の染色体 58/浪人 60/酒場 62/別れ 64/村の領域 66
画家 68/数式 70/顔 72
3章 民衆の記憶
遺伝子 76/所感 78/若い娘 80/人類の記憶 82/生きたものの記憶 84
有事 86/木炭 88/居庸関 90/天壇 92/歌 94/絶滅危惧種 96
あとがき 100
【詩篇紹介】
流れと群れ
昭和二十一年、三十一歳の母は妊娠と極端な粗食のため、次
第に視力を失い、薄暮から未明にかけては漆黒の闇に生きて
いた。全くその機能を喪失した目から、涙の湧いて落ちるの
を、その時むしろ、感動をもって私はみつめていた。
その年五月、九つちがいの弟は生まれた。
十九年後、大学の入学試験に落ちた弟を前にし、私は慰める
言葉の代わりに、炎を反映し、赤い翼を見せていたボーイン
グB29の話をしてやった。
昭和二十年三十日、死ぬことだけを考え、無意識に歩いてい
た生き残りの流れの一つは皇居前広場、もう一つは上野駅へ、
そしていまひとつの群れは、不思議な光芒をはなちながら、新
宿駅へと続いていたのだった。