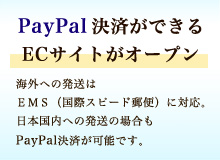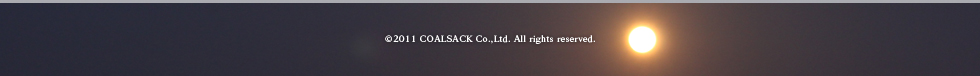細枝のけむる裸木の奥に/辛夷の蕾が白い/鳥のこだまやこもりあう大気をめぐらせ/いっせいに噴き上がるいくつもの一輪/遠ざかる枝先をかすめて/一本の白い花群は炎となってゆらめき/色褪せた枯色を截り拓いている/肌寒い風のまにまに誘われる宴の/ぐらりと揺れ戻す白炎のありか/呼び戻した地霊の疼き/目覚めた繭から/羽化するごとく咲き出る時刻(詩「花群」より)
| 解説文:横田英子、佐相憲一、鈴木比佐雄 |
| 四六判/224頁/上製本 |
| 定価:1,620円(税込) |

発売:2012年6月7日
【目次】
第一詩集『距離』(一九五九年刊)より
距 離
はにわの眼
藍に寄せる
夜の構図
海
一匹のはえ
めぐるもの
落 葉
馬の像に
一つの愛
影
橋
第二詩集『時の記憶』(一九六一年刊)より
眼 に
かげろう
盲目のひだ
白と黒
彫 像
二月の芽
年 輪
不在にひそむもの
曲 る
沃 野
ローソクの火
深夜の森
第三詩集『原型』(一九六二年刊)より
黒 蝶
染まる
無限に
隔 絶
明るい夏の日のために
ひまわり
原 型
海 雪
対坐する日
苔
遠すぎるので
雨
第四詩集『影絵』(一九六二年刊)より
ひびき
あふれるものを
晩 夏
夜の木立
みずうみ
晩 秋
初 冬
音 は
砂と影
迷 路
横 顔
呼ぶ声
序 章
第五詩集『春の容器』(一九六七年刊)より
春の容器
静 物
ゆらぐ朝
退き潮
埋み火
木もれ陽
ゆらめき
ひろがる
はじまる
虹
澄 む
放 つ
第六詩集『背中を』(一九七五年刊)より
風のない夜
眠りは
ひかりのなかで
移ろい
幻 花
夕 日
山茶花
背中を
雪 夜
春 雷
駈ける
眠りのなかに
第七詩集『灯影』(一九九三年刊)より
顫 音
霧の朝
薔薇に
夏の径
白 梅
彼岸過ぎ
ぬくもりを
穂 波
寝 姿
小こうもり
陽の中を
校門のある街角で
第八詩集『埴輪の目』(一九九四年刊)より
花 群
朝 は
須磨浦
谷間に
蝉しぐれの中で
雨上がりの朝
鳥 影
立枯木
空洞に
遠い日を
川面に
漂う船
第九詩集『日没の稜線』(一九九九年刊)より
眼 は
呼び声
曼珠沙華
沈丁花
潮騒ぐ日
焚 火
極限の日
日暮れに
川沿いの道
萩の咲く庭
別れを積んで
夕陽の中を
第十詩集『冬芽』(二〇〇三年刊)より
独りの棲む部屋
繭
白い道
西の街
荒磯で
冬 芽
菩提樹の道から
開花の微音が
滅びの前に
蓮池から
一隅のひかり
影を踏んで
網走海岸
第十一詩集『浅春の途』(二〇一〇年刊)より
埋まってゆくとき
浅春の途
水引草が
山懐が
刻み残して
足踏む位置から
踏みとった地の上で
時のかけらが
輝きは
語らいの刻
花影を踏んで
冬の終り
幼い日
放つとき
宿り木の譜
未収録詩篇
原子力の行方は
橙色に包まれた街
志半ばで散った二人の兄
影を踏む
福島の災禍は
詩論・エッセイ集『思索の小径』(二〇〇九年刊)より
御影の頃
仁川橋あとさき
早とちりその余話
水脈に棲む葦
誘いの径
解説・詩人論
鳥巣郁美詩選集から その生きてきたあかし 横田英子
生の動きを見つめて引き寄せる複眼の詩人 佐相憲一
小径を歩行し美を思索する人 鳥巣郁美詩論・エッセイ集『思索の小径』に寄せて 鈴木比佐雄
円環する純粋経験を詩作の文体に刻む人 鳥巣郁美詩集『浅春の途』に寄せて 鈴木比佐雄
略 歴
詩篇を紹介
「浅春の途」
枯色の野を踏んでいる
来し方の荒涼もまた
寒さを孕んで重なってゆく
名残の冷気の行き戻るその日
裸木はわずかに煙る細枝を持つ
凋落の果てを見透かしてゆく野の
視野の底を熟春が行き交い
是非もない萌色も零れた花々も
紡ぎ誘う果肉の姿も
ずいと続く道程に確かさを弾ませていた
終焉を凝視める如き目前の
途上の陥穽に竦み立つ日
一望の果てに呼び戻してゆくのは
潮騒を呼んだ或る日の堆い海の言伝
虚ろさに挑む分厚い掌
消し色の残欠を煽って
時に耳底に響き残る
夜半にふいと届く梟の声音
共々に見透かす野の終りを不確かに急き蒐めて
更になお立ち戻ってゆく浅春の灯